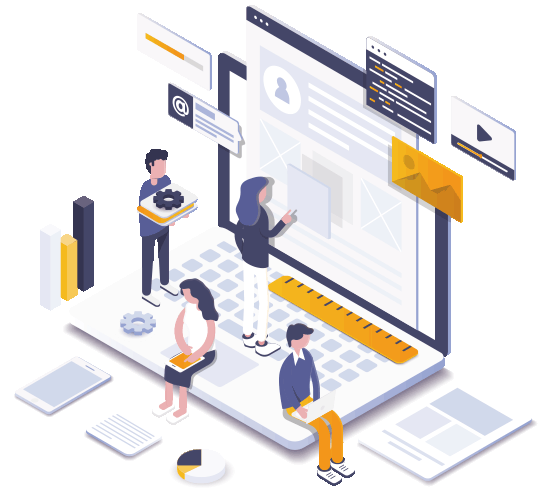- 課題からみる
-
- ホーム
- 課題別・解決ソリューション
- システムの内製化のメリット・デメリットや実現に向けてのポイントを解説
- DX
- システム開発
- すべての部門
システムの内製化のメリット・デメリットや実現に向けてのポイントを解説
2023.07.31更新日:2025.11.20
現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推し進める企業が増えている中、システムの内製化が注目されています。
本ページではシステムやソフトウェアの内製化によるメリット・デメリット、内製化を成功させるためのポイントを解説。さらに内製化をスムーズに推し進めるためのツールをご紹介します。

システムの内製化が注目されている理由
「内製化」とは、システムの開発や運用を外部の企業へ委託せずに自社内で行うことを指します。
これまで日本国内では、自社のIT業務アプリやシステム開発を開発する際、開発者やシステム設計を理解できる人材が社内にいないため、専門のSIer(エスアイアー、システムインテグレーター)に外注するケースが主流でした。
しかし、近年デジタル・IT環境やビジネス環境が急速に変化する中で、市場のニーズや法律の変化に合わせてビジネスモデルの変革や改善を余儀なくされています。従来通り外部のSIerにアウトソーシングをすると、見積もりなどの商談プロセスが発生し、発注から納品までにタイムラグが発生します。納品される頃には「発注したころにはこれでよかったが、今はこの機能じゃ足りない」という要望の変更が発生するのも珍しくありません。
その点、社内で作れるようにならなければ、仕様の変更が比較的容易です。
こういった脱外部業者依存・アジャイル経営への関心の高まりを背景に、システム内製化への注目が高まっています。
システム開発がSIerから社内開発にシフトするのも、時代とともに変わっていくビジネスモデルの一つといえそうです。
システムを内製化するメリット
システム開発を内製化するメリットとして、「柔軟かつスピーディーな開発が可能」「ナレッジやノウハウの蓄積」「トータルの費用の削減」の3つが主に挙げられます。それぞれ順に解説していきます。
システム内製化のメリット1.柔軟なシステム開発がスピーディーにできる
自社でシステム開発を行う際、システムを実際に活用する現場のメンバーが携われば、現場の声を反映したより使いやすいシステムを構築できます。また外注先のSIerとの契約手続きやスケジュール調整といったやり取りを省略できるので工数や時間の削減にもつながり、より迅速な開発が可能となります。開発中の仕様の変更にも社内の調整のみで対応できるため、柔軟な開発が可能となるでしょう。
システム内製化のメリット2.社内にナレッジやノウハウを蓄積できる

システム開発を全面的にアウトソーシングした場合、システムに精通した人材が社内におらず、当時アウトソーシングを担当したスタッフの退職や仕様書の不在により、時間の経過とともにシステムがブラックボックス化していく事態がよく報告されています。
システムの内製化によって社内メンバーが開発に携わり運用や保守業務まで行うようになれば、システムの内部に関するナレッジやノウハウの蓄積ができます。
不具合が発生した際の原因や対応方法も容易に社内で共有できるようになるでしょう。
システム内製化のメリット3.トータルの費用を削減できる

内製化を行い自社でシステムを開発、運用する場合、長期的にはコストの削減が期待できます。
システム開発のような専門性の高い業務ならば、外注した場合に高額の委託費が発生し、保守、機能の修正など追加作業が発生することでさらに費用が上積みされていきます。
システムの内製化により、IT人材の雇用や社内での教育、開発ツールの導入などの初期費用はかかりますが、長期的にはコストダウンを実現できるでしょう。
システムを内製化のデメリットと対処すべき3つの課題
システム内製化のデメリットは「急には始められないこと」です。
主たる3つの課題「IT人材の確保や育成」「品質の維持」「作業の属人化および離職リスク」の課題について、順に確認していきます。
システム内製化に向けた課題1)IT人材の確保や育成が難しい

社内でシステム開発を行うには、専門スキルを持ったエンジニアが必要になります。IT人材が不足している現在、求めるスキルを持った即戦力となる人材は簡単に見つからないのが実情です。仮に採用できたとしても、優秀な人材に自社で働き続けてもらうには見合った給与を支払う必要があります。
また既存社員に相応のIT知識や技術を習得してもらうためには研修などが必要ですが、急な業務変更に該当社員も戸惑うでしょう。研修費用も時間もかかるため、既存社員の育成とシステムの内製化を同時に進めるのは容易ではありません。
システム内製化に向けた課題2)システムの品質が維持できない可能性がある
システム開発を外部のSIerに委託する場合、各社が設けている品質基準をクリアした製品が納品されるため、一定の水準が担保されています。
一方自社内のエンジニアは、外注と比べて技術、実績、経験の面で不足していることが考えられます。
そのためシステムを内製化する際にクオリティが落ちる可能性は否定できません。システムを長期にわたって運用し必要な保守や改修を重ねていくためには、自社エンジニアが見合ったスキルを身に付けていく必要があります。
システム内製化に向けた課題3)作業の属人化や離職リスクがある
業務の内容や進め方を特定のメンバーしか把握できていない状態を作業の属人化といいます。専門的な技術や知識が要求されるシステムの内製化では、限られた人員に業務が集中してしまい属人化を引き起こすリスクが考えられます。
また担当者が離職や異動によって業務を離れた場合に懸念される、システムのブラックボックス化は避けなければなりません。万が一、ブラックボックス化してしまった場合、追加したい機能や修正したい仕様があってもシステムの中身を熟知したメンバーがいないため、手を出せなくなります。
DXにおける要注意ワード:「システムのブラックボックス化」とは
あるシステムで、“入力値(インプット)と出力値(アウトプット)の組み合わせはだいたいわかるが、中でどのように設計されているかわかる人が誰もいない” という状態です。
システムの設計図や仕様書、説明書などが明文化され共有されておらず、「中でどのように動いているか知っている人」が引継ぎをせず全員退職・異動したりした場合、システムのブラックボックス化が発生します。
システムの内製化を実現するポイント
このように内製化にはメリットとデメリットがあります。デメリットとなるリスクを避け、内製化の導入を成功させるためのポイントを紹介します。
システム内製化実現に向けて:社内で使用されているシステムやドキュメントを把握する
内製化を進めるにあたって、まずは社内にあるシステムの棚卸しから始めると良いでしょう。現在使われているツールやドキュメントを把握し、稼働しているシステムの現状を確認します。最新版にアップデートされていないものや、社内全体で共有されていないものなど、システムの課題が整理されるはずです。
その上で、内製化の優先順位を考えます。基幹となり安定性が求められるようなシステムは、変化させずそのまま残しておいた方が良い場合があります。課題が多くボトルネックとなっている箇所、複数のものを一つのシステムに統合できる箇所などから順に、内製化を進めていきましょう。
システム内製化実現に向けて:コーディングスキルがなくても使えるツールを導入する
自社内でシステムをスクラッチから開発する場合、プログラミングスキルを持つ人材が必要です。そうしたスキルを持つ人材を確保し、膨大な工数を掛けて開発を行うには時間もコストも掛かります。そこでIT知識がなくても簡単に利用できるツールを導入するのがおすすめです。
2023年現在、プログラミング能力がなくてもシステムの開発ができる「ノーコードツール」が複数あります。既存のSaaSとSaaSの連携というものや、データベースをもとに業務アプリを開発できるものなどから着手するとよさそうです。自社にあったものを探しましょう。
開発・内製化をはじめるにあたり、システムのブラックボックス化防止のため、仕様書やノウハウやマニュアルを共有できる「情報共有ツール」もあわせて導入しましょう。
- 【2024年版】ノーコード開発の基礎知識|メリットや開発ツール、注意点を解説【リックソフトの導入ユースケース付き】
- ノーコード開発、ローコード開発の基礎知識と、リックソフトで導入しているローコード・ノーコード開発ツールiPaaS(アイパース)「Workato(ワーカート)」の導入効果を紹介しています。
「Confluence(コンフルエンス)」 を活用した社内ドキュメントの一元管理
システムの内製化のようなプロジェクトでは、チーム内でドキュメント書式やルールが統一されていなければ円滑な情報共有は望めません。重要なファイルやメールがいろいろな場所に分散していると、必要な情報にアクセスするにも時間が掛かってしまいます。また、ドキュメントやファイルが更新されても新しい情報がチーム内で直ちに認識されないことも考えられます。
これらの課題を解決し、効率的なコラボレーションを実現するのが企業向け情報共有ツール「Confluence(コンフルエンス)」です。Confluenceには以下のような特徴があります。
- ドキュメントをツリー構造で管理し、簡単に情報を検索できる
- 豊富なテンプレートにより目的別に容易に、共同でドキュメント作成が可能
- ホワイトボード機能で共同のブレインストーミング作業やUML図などの作画も可能
- 共同編集、コメント、通知、権限制御などチームワークを促進する機能
Confluenceならシステム設計・開発・管理のノウハウやナレッジを体系的にまとめ、スムーズにメンバーへ共有できます。
- 社内の情報を 蓄積&活用する
ナレッジマネジメントツール Confluence(コンフルエンス) 
- 製品について詳細はこちら
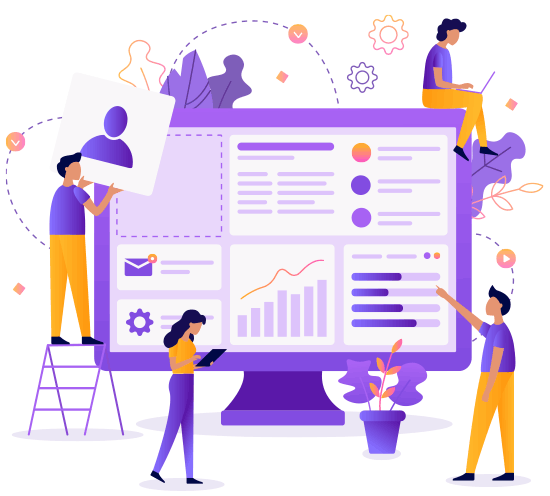
「Jira Software(ジラ・ソフトウェア)」 を活用したシステム開発
システムの内製化に伴う開発の進行を管理するための強力なツールが「Jira Cloud(ジラ・クラウド、旧名称Jira Software)」です。Jira Cloudはプロジェクト進捗や各メンバーのタスクを見える化し、チーム全体で情報を共有することができます。また、以下のような特徴を持っています。
- どのタスクが、だれが担当しているのか・どの進捗ステータスなのかを、複数人が同時に記入できる(非同期型コラボレーションツール)
- かんばんボードやスクラムボードによりタスク進捗の全体像を可視化できる
- 開発期間を定義するスプリント、作業の進捗を反映するバーンダウンチャート、平均作業量を可視化するベロシティチャートによりチーム作業を透明化
- 豊富なレポート機能で、チームのメンバーが入力した課題の状況をリアルタイムに共有できる
- ドラッグ&ドロップなどの直感的な操作が可能
- 仕様書作成にも役立つ社内Wiki「Confluence」やソースコード管理ツール「BitBucket」との高い連携性
Jira Cloudは短いサイクルでPDCAを繰り返すアジャイル開発を後押しする豊富な機能を備えています。
- グローバルで利用されているアジャイル開発チーム向けの
タスク管理、プロジェクト管理ツール 『Jira Cloud』 
- 製品について詳細はこちら