- 課題からみる
-
- ホーム
- 課題別・解決ソリューション
- 【脱エクセル】プロジェクト管理ツールとは?!使うメリットVSデメリット| 失敗しない選び方やかかる費用を解説
- DX
- ビジネス部門
【脱エクセル】プロジェクト管理ツールとは?!使うメリットVSデメリット| 失敗しない選び方やかかる費用を解説
2023.09.29更新日:2025.3.21
DX(デジタルトランスフォーメーション)や業務効率化施策の一環として、「プロジェクト管理ツール」を導入する企業が増えてきています。
しかし「無料プランがあるものもあるが、業務で使うものを無償で使っていいものか」「組織内でITリテラシーに差があるため、定着するかが課題」といった課題を抱えている方もいると思います。
この記事では、企業・チーム向け「プロジェクト管理ツール」の種類や選び方を解説します。自社に合ったツールを検討する際の参考にしてください。

プロジェクト管理ツールとは

プロジェクト管理ツールとは、複数人が参画する1つの業務・プロジェクトの状況を管理したり、複数の業務・プロジェクトの状況をまとめて管理するのに役立つデジタルツールです。
そもそも、プロジェクトとは?
プロジェクトと聞くと、何百人単位が動き、何か月・年もかかるプロジェクトを監督する人が工数や予算を管理するために使うというイメージがわくかもしれません。もともとの意味は、目標を達成するために策定した計画やその行動のこと。プロジェクトマネジメントの専門家の橋本将功氏は、「マニュアルがなくて突発的に発生する取り組みはすべてプロジェクト的なものと認識したほうがいい」とも話しています。
プロジェクトチームはそれを実現するための組織です。近年は数人単位のチームでプロジェクトメンバー同士のコラボレーションを促すツールも提供されています。
非ビジネスの領域では「引っ越し」や「部屋の模様替え」などをイメージしてください、これらをプロジェクトとして、家族や友人たちで切り盛りをしていくには、「なにを(作業名)」「いつまでにやるか(納期管理)」「優先度」といった項目を管理するとスムーズになるとわかると思います。
令和に必須のビジネスツール:デジタル化したプロジェクト管理ツールのメリット
チームでのプロジェクト管理は、オフィスにあるホワイトボード、各個人のスケジュール帳、またはクラウド環境や社内のサーバーにあるエクセルソフトでされている方が多いでしょう。
働く場所が多様化し、コアワークタイムなど非同期型の働き方が浸透してきた現在、物理的な情報共有には限界が出てきます。また、各個人のスケジュール帳やメモ帳、デジタル化したタスク管理ツールに依存する場合、情報の同期漏れや認識の漏れが発生します。
ファイルサーバーやクラウドの表計算ソフトはビジネスの場で根強い人気を誇っていますが、「検索しても検索結果がしづらい」「セルに入力した長文の情報が消えてしまった」という困りごとも発生しています。
プロジェクト管理ツールは、プロジェクトを円滑に進めていく上で必須となる以下の要件を1つのツール上で管理できるツールです。
- プロジェクトに紐づくタスクの進捗管理と予算管理
- タスクや関連業務の優先付け・管理
- チームメンバー毎のタスク管理・納期管理
- プロジェクトに関する情報の管理・共有(コラボレーション)
- 課題検討やQA(品質保証)の状況管理
- タスク/成果物に関する承認ワークフロー
プロジェクト管理ツールを導入していない場合、上記をそれぞれ別のエクセル(Excel)や紙などで管理したり、都度都度どこまで進んでいるかや変更点を担当者にメールや口頭で説明を求めている方が多いかと思います。プロジェクト管理ツールを導入すると、これらの業務を1つのITツール内で完結できるようなイメージを持つとよいでしょう。
プロジェクト管理ツールを導入するメリット

プロジェクトひとつひとつの状況がプロジェクト管理ツールできちんと管理されていれば、現状把握や変更時の計画修正も導入前より容易になります。
また、プロジェクトマネージャーだけではなく、プロジェクトメンバーもプロジェクトの全体像を確認できるため、チーム内での状況共有が容易になるのも大きなメリットでしょう。

- プロジェクト管理ツール「Jira」は10ユーザーまで無料!
- 今すぐAtlassian Cloudを10ユーザーまで無料で試してみませんか?
プロジェクト管理ツールを比較するときのチェックポイント
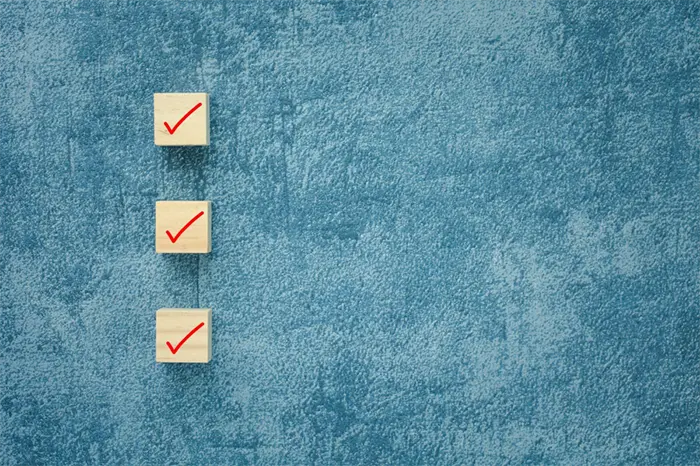
ここまでプロジェクト管理ツールを大きく3つのタイプに分けそれぞれのポイントを解説しましたが、実際にはこれらの線引きは曖昧です。また、同じタイプのプロジェクト管理ツールでも、各サービスごとに特徴があります。
そのため、ここからはプロジェクト管理ツールを比較し、選ぶときにチェックしたいポイントについて解説していきます。製品比較ランキングなどを見る際にも、是非参考にしてみてください。
プロジェクト管理ツールを選ぶ際のチェックポイントは、次の5つです。
- 現場のニーズにあわせた機能
- 費用とその効果
- 管理データの保存場所(データリージェンシー)
- 操作性と、ヘルプデスクの有無
- 業務ですでに導入済のSaaSとの連携性

- プロジェクト管理ツール「Jira」は10ユーザーまで無料!
- 今すぐAtlassian Cloudを10ユーザーまで無料で試してみませんか?
現場のニーズにあわせた機能
プロジェクト管理ツールにはカレンダー機能やチャットツールの連携など、複数の機能がありますが、何を目的にプロジェクト管理ツールを導入するかを今一度確かめましょう。現場のニーズを確認したうえで、優先すべき機能の有無を整理しましょう。
例えば、以下のような例が挙げられます。
- コミュニケーションや情報共有を目的とする場合「情報共有機能」を重視
- 社員のパフォーマンス向上を目的とする場合「タスク管理機能」を重視
- 大規模プロジェクトを管理する場合、計算上の工数と実際の工数を管理する「工数管理機能」を重視
- 複数プロジェクトを管理する場合「複数プロジェクト管理機能」を重視
これらのように「プロジェクト管理ツールの導入目的が達成できるか」という観点から、重視する機能について詳細な確認・検討することをお勧めします。
費用とその効果
プロジェクト管理ツールはユーザー数単位・利用年単位で費用が決まるものが主流ですが、ユーザー数や機能を制限はあるが無料で使えるもの、OSSソフトで自社で管理するものもあります。有料の場合、料金体系は従量課金型と月額固定型の2つに大別されます。
いずれの場合も、利用期間・利用目的に合っているか、という観点でよく検討をする必要があるでしょう。
導入したあとのゴールとなる“状況”の設定しておく良いでしょう。ツールをメンバーに定着させことがゴールなのか、メンバーが使えるようになったうえで組織体質を変えるのがゴールなのか、ツールに溜まったデータをもとに分析して組織課題や経営課題を見つけることがゴールなのかで、選ぶ製品も変わってきます。そしてそのツール導入で得られる効果も大きく異なります。

- プロジェクト管理ツール「Jira」は10ユーザーまで無料!
- 今すぐAtlassian Cloudを10ユーザーまで無料で試してみませんか?
管理データの保存場所(データリージェンシー)
管理データの保存場所についても、プロジェクト管理ツールを選ぶ上では重要なポイントです。大きく、「クラウド型」と「オンプレミス型(インストール型)」の2種類があります。
クラウド型は、サービス提供側がクラウド上で保管します。クラウドサービス場合、データセンターがどこにあるのか(日本国内なのか・海外なのか)社内の規定に沿っているかも確認しましょう。
オンプレミス側は、自社でデータの保管場所を用意する必要があります。
クラウド型
管理データがクラウドベンダー側のサーバーに保存され、自社からはインターネット経由で接続して利用する形式を「クラウド型」または「クラウドアプリ」「SaaS」と言います。
■メリット
- スマホやパソコンなど、複数のデバイスから同時にアクセスが可能
- 初期費用がかからない(かかる場合、低額なケースが多い)
- 自社サーバーの管理が不要
■デメリット
- インターネットに繋げる環境でないと利用できない
- 自社の特性に応じたカスタマイズが困難
- サービスの利用可能時間などがプロジェクト管理ツールサービス提供元に依存する
オンプレミス型(インストール型)
自社内のサーバーなどにプロジェクト管理ツールを導入し、自社内で管理データを保有・運用していく形式を、「オンプレミス型(インストール型)」と言います。
■メリット
- 自社の特性に合わせたカスタマイズが可能
- 自社内の環境からであればある程度自由に利用可能
■デメリット
- 自社サーバーの設定が必要な分、導入に初期費用や手間がかかる
- 導入後、保守業務を自社で行う必要があり、クラウド型よりランニングコストかかる

- ファイルサーバの管理はもう限界?
クラウドへの移行を検討するタイミングや移行方法、移行の際の注意点を解説
操作性と、ヘルプデスクの有無
プロジェクト管理ツールを導入したとしても、そのツールがエンドユーザーにとって使いづらい場合、「結局利用されず、導入費用を回収できない」といった失敗にに陥りがちです。これを回避するために、操作性の良さ・ITリテラシーの低い社員向けの研修など使い方を指南する支援材料があるかどうかも併せて確認しましょう。
多機能なツールを選ぶと実施できることは多くなりますが、使いこなすまでに教育コストがかかる可能性もあります。
自社の業務で必要な内容と照らし合わせつつ、誰もが使えるシンプルなユーザーインターフェース(操作画面)であるかといった点も重要です。しかし、ユーザーインターフェースはよくても、導入後に得られる効果が少ない場合は、導入のコストと結果が見合いません。利用方法を習得するための研修等を含めたアフターフォロー制度や、管理者以外のエンドユーザーの質問にも受け答えるヘルプデスクがあると、「使い方がわからないから社内に浸透しない」と阻害要因を取り除くことができそうです。
SaaSとの連携性
日本でも10個以上のSaaSを導入している企業は少なくありません。社内でコミュニケーションツール(TeamsやSlack)やカレンダーツール(GoogleカレンダーやOutlook)、Google SpreadsheetなどのSaaSを利用している場合、「すでに導入しているSaasとの連携が可能」かというのも重要なポイントになります。
「プロジェクト管理ツールで登録したタスクをカレンダーへ反映させる」、「コミュニケーションツールでのやり取りをプロジェクト管理ツールへ取り込む」など、SaaSとの連携が可能であれば、よりスムーズなプロジェクト運営が実現できます。
実際の使われ方を想像しつつ、どのような形で連携が可能なのかをしっかり検討することが大切です。
自社に合ったプロジェクト管理ツールを導入し、業務効率化を目指そう

ここまでプロジェクト管理ツールの基礎知識や、選ぶ際のポイントについて説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
プロジェクト管理ツールを導入することで、進捗・タスク管理やプロジェクト情報の一元化など、様々な業務改善効果が期待できます。
従来エクセルなどでプロジェクト管理を行ってきたものの、やりにくい・不便だと感じたことがあるのであれば、これを機に是非プロジェクト管理ツールの導入を検討してみてください。
また、Ricksoftでは、システム開発の現場で広く活用されているAtlassian社のパートナー企業として、プロジェクト管理ツール(Jira、Confluenceなど)を取り扱っています。
製品やサービスのライセンス販売のみでなく、組織に定着させるための伴走型導入支援、運用サポートなど、「自社の課題に沿ってプロジェクト管理ツールを上手に使う」ためのサービスを提供しています。
この記事を読んで、プロジェクト管理ツールを導入してみたいと考えている方は、是非以下のHPもご参照ください。
- グローバルの多くのチームが利用しているプロジェクト管理ツール。
アジャイル開発だけでなくビジネス部門でも。 
- 製品について詳細はこちら
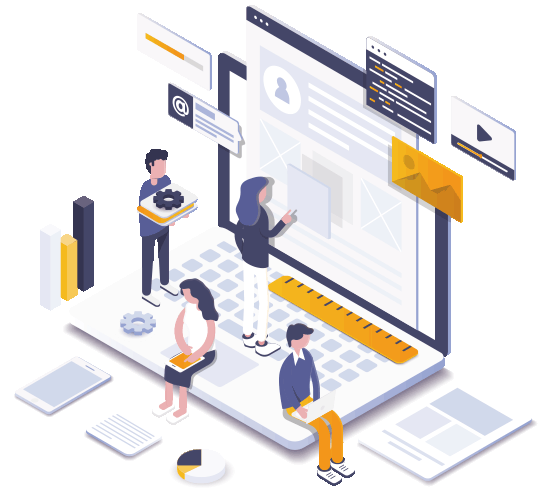
- プロジェクト管理ツールの導入事例
マツダ株式会社 - 複雑化が進む自動車の開発プロジェクトを支えるアトラシアン製品群
Jiraをはじめ、データ連携ツールの併用でデータの可視化も実現 -

- 導入事例を読む



