- 課題からみる
-
- ホーム
- 課題別・解決ソリューション
- 業務の属人化とは? 懸念されるリスクや属人化の解消・防止方法を解説
- 属人化防止
- すべての部門
業務の属人化とは?
懸念されるリスクや属人化の解消・防止方法を解説
2023.07.31更新日:2023.12.14
業務の属人化(特定の業務やタスクがある組織内の特定の個人に過度に依存している状態)は人材の流動がより一層激しくなった昨今において、多くの企業が頭を悩ませる課題です。テレワークやフレックスタイム制など働き方の多様化が進むことで、情報のサイロ化が起きやすくなり、属人化に対する問題は重要度を増しています。
本ページでは、業務の属人化に悩んでいる経営者や業務責任者、人事担当の方のために、業務の属人化によって懸念されるリスクやその解消・防止方法、おすすめのツールについてご紹介します。

業務の属人化とは?
業務の属人化とは、ある業務の対応方法や進捗状況の把握などが特定の担当者にしか分からず、その人に依存してしまう状況を指します。すなわち組織にとって業務が「ブラックボックス化」した状況となり、担当者が退職や休職をした際に対応できる人が居なくなってしまうというリスクがあります。こうしたリスクを回避し、組織全体で業務の生産性を向上させるために、多くの企業が「業務の属人化」を課題として捉えています。
業務の属人化が起きる背景
業務の属人化を引き起こす背景について見ていきましょう。属人化しやすいケースとして以下の4つの事例を紹介します。
1つ目は「業務が専門的なケース」です。専門性の高い業務の場合、知識や経験が必要となるため特定の担当者しか対応できない場合が多く、属人化しやすい傾向にあります。例えば過度にカスタマイズしたエクセルの設定など、設定した人が「どんなカスタマイズをしたか」という仕様のメモなどが残っていない場合、誰も動かせなくなって困る、というケースはよく聞きます。
2つ目は「情報共有をする時間が取れないケース」です。特定の担当者へ業務が集中していることやタイムマネジメントができていないことが原因となり属人化を引き起こします。また、フレックス制度などで終業時間があわず、コアタイム時間もほかの業務でいっぱいとなり、業務の認識合わせをするチャンスを逃してしまうことも原因の一つです。
3つ目は「作業を独占することで社内での地位を確立するケース」です。特定の担当者に業務が依存してしまうということは裏を返すと、組織内でその担当者の優位性が保たれるということになります。社員が自分の立場を守るため、意識的に属人化を引き起こすケースも存在します。
4つ目は「管理体制が原因で属人化が起きてしまうケース」です。管理職が特定の従業員に過度に依存するため、その人物に業務が集中してしまいます。この状況が続くと、業務情報も属人化してしまい、業務が集中している人材は休みづらくなります。
業務が属人化が引き起こす問題点
業務が属人化したまま放置すると「業務効率の低下」「品質の維持」「退職時の問題」「業務の不均衡(特定の人物への業務過多)」など、さまざまな問題が危惧されます。「組織への影響」「個人への影響」2つの切り口で、発生しがちなリスクを見ていきましょう。
組織への影響:業務の効率化が図りにくい
1つ目のリスクは、業務の効率化が図りにくいことが挙げられます。業務の属人化によって作業の工数や手順などがブラックボックスとなり、業務効率を改善するために必要な正しい情報を得ることができません。
さらに特定の担当者が病気や出張などで不在となる場合には、ノウハウがないため他の社員が代わりに対応することができず、作業がストップしてしまいます。こうした一つの業務停止が起点となり、その他にまで及んで業務遅延を招くリスクがあります。
組織への影響:品質にばらつきが出てくる
2つ目のリスクは、自社サービスの品質を維持しにくいということです。
業務の属人化が起きているということはマニュアルや手順書が存在しない可能性があります。あったとしても最新の情報に更新されていないケースも考えられます。結果として、作業を担当する者によって品質に差が生じる可能性があります。
また専任の担当者がいる場合において、前述のように何かしらの理由で他の担当者へと代わりに対応が求められる際には、なおのことミスや品質の低下などのリスクが生じるでしょう。そして「不具合に気付かない(気付ける体制でない)」という致命的な実態であることから、「欠陥」「信用問題」など大きなトラブルへと発展する危険性があります。
組織への影響:人材流動時に業務が停滞しやすい
3つ目のリスクは、人材流出時に業務が停滞してしまうことです。人材退職前にも後任者の引継ぎに時間がかかり、業務が停滞します。また引継ぎ漏れがあった場合、後任者はイチから作業をするため、業務が停滞します。結果として、前述のように品質が保持されなくなります。
業務の属人化にはさまざまなリスクが潜んでおり、属人化の傾向が見られる場合や可能性がある場合はすぐに対処すべきであることが分かりました。これらのリスクを回避するにはどのような解消、防止方法があるのでしょうか。ここでは具体的な方法について見ていきましょう。
個人への影響:休めないストレス
特定の業務が一人に集中すると、その人に対する過度の負担やストレスが生じます。仕事が多すぎるゆえに休めない・「休むとほかの人の業務が滞るから」という使命感で休みにくくなります。
個人への影響:キャリアパスが描けなくなる
特定の業務に専念するため、他の業務のスキル習得が遅れがちになります。その結果、キャリアパスが描きにくくなります。
特に生成AIのプロンプトエンジニアリングや動画マーケティング、ビジネスビジネス・インテリジェンスなど、あらゆる場面で新しい技術がどんどん生まれトレンドが変化する昨今、スキルの幅が広がらないことは本人に危機感を与えます。
業務の属人化を解消・防止する方法
業務の属人化にはさまざまなリスクが潜んでおり、属人化の傾向が見られる場合や可能性がある場合はすぐに対処すべきであることが分かりました。これらのリスクを回避するにはどのような解消、防止方法があるのでしょうか。ここではすでに属人化が進んでしまった組織がとるべき具体的な行動計画と、属人化を未然に防ぐ方法提案します。
属人化を解消したい組織がとるべき対応:業務の見える化を行う
業務の属人化を解消するための第一歩として、業務の見える化を行う方法があります。具体的な取り組みの代表例は、下記の通りです。
| 業務の見える化の方法 | 内容 |
|---|---|
| 業務の洗い出し | 業務のすべてを洗い出し、改善点や優先順位を把握 |
| フローチャートの作成 | 業務プロセスを視覚化する |
| 進捗管理 | リアルタイムでの状況把握と蓄積 |
| ナレッジ共有 | ノウハウやスキルなどの全てを共有 |
これらを実践、継続することで共有すべき情報が可視化され「業務効率の低下」や「退職時の問題」などのリスクを回避し、属人化の解消を進めることが期待できます。
属人化を解消したい組織がとるべき対応:コミュニケーションとコラボレーションの強化
ひとりの人に業務が集中する1to 1のコミュニケーションではなく、1to多数または多数to 1のコミュニケーションがとれる風土に変えていきます。
具体的には、メールや電話、チャットツールのダイレクトメール、口頭などの1to1の手法から、コラボレーションツールやチャットツールのグループスレッドなど、ほかのメンバーも状況がわかるような場所で確認をするように心がけていきましょう。
時間はかかるかもしれませんが、「他の人からも情報が見えるようにする」風土を作っていくには継続鹿ありません。
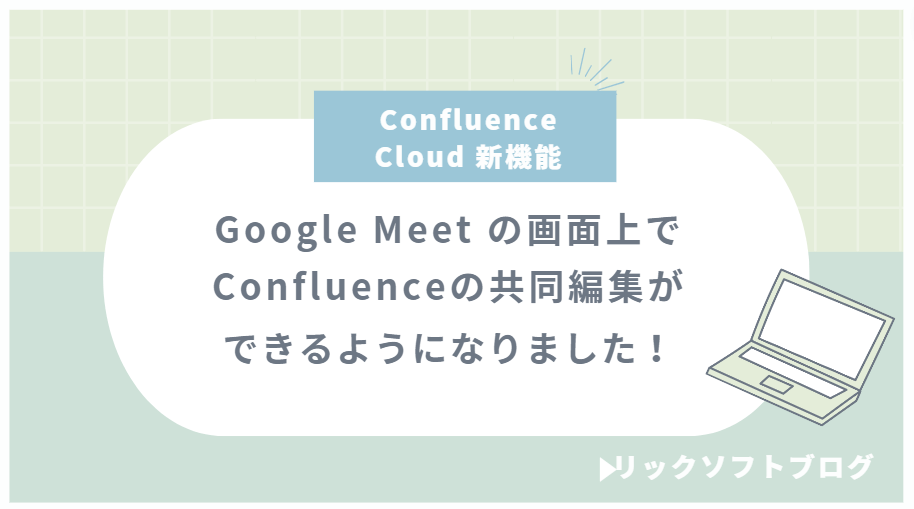
- <Google Meet 上でConfluenceの共同編集ができるようになりました>
- 新機能紹介|Confluence Cloud「Google Meet との連携」
属人化を解消したい組織がとるべき対応:マニュアルを作成する
業務の属人化を解消する上でマニュアルの作成は必要不可欠です。業務担当者を中心に、見える化した作業のフローや内容を第三者の誰が見ても理解できるようにまとめましょう。マニュアル作成における基本的なポイントは下記の通りです。
- 業務の目的を記す
- フローチャートを用いて全体像を記す
- 詳しい手順を記す(業務の階層構造に合わせる)
- トラブルの対処法やいくつかの事例を記す
- 図や写真、イラストを用いて記す
以上のポイントを押さえると、誰でも業務がわかるマニュアルを作成することができます。
業務が属人化しないため組織がとるべき対応:作業やマニュアルの定期的な見直し・改善をする
作成したマニュアルを定期的に直し、改善することで業務の効率と品質が保たれます。見直しのタイミングは主に下記の2パターンを想定しておきましょう。
- 半期、四半期など定期的に見直す
- 業務ルールの変更や新たな問題点が見つかった場合などに都度見直す
現場では実際の日々の業務を通じて、気付きがあった際に改訂が必要な箇所を記録し、まとめておくことが重要です。
マニュアルを改定する際、過去のマニュアルは削除するのではなく、「なぜこのような業務になったか」を未来の人がわかるよう、履歴を残しておくとよいでしょう。
マニュアル改定後も繰り返しPDCAを回していくことで、属人化防止の効果を発揮します。
業務が属人化しないために組織がとるべき対応:情報共有をしてノウハウをナレッジ化する
マニュアルにはこれまでの改訂履歴を含めて社内に情報共有をし、ノウハウをナレッジ化して蓄積することが大切です。その他「社内FAQ」「技術ノウハウ」「議事録」など、属人化を防止する上で必要なドキュメントは無数に存在します。
ここういった情報を効率的に管理するには、ナレッジマネジメントツールの導入がおすすめです。ツールを選ぶ際は、検索性能の高さやテンプレートのカスタマイズ性、閲覧・編集権限の柔軟性、モバイルアクセスの可否、他システムとの連携ができるかどうかなど、基本的な機能をチェックしておきましょう。
ベーシックな機能を搭載していることを踏まえた上で、自社の業務要件、課題に合わせた付随機能が用意されているか確認をすると良いでしょう。
ツールを選ぶ際の注意点
ツールを選ぶ際の注意点として「セキュリティ対策がしっかりなされているものを選択する」ということが挙げられます。ナレッジ共有管理ツールでは機密性の高い情報を取り扱うこともあるため、情報漏洩のリスクは回避しなければなりません。「アクセス制限」や「アクセスログ機能」を完備したツールを選択することで、高いセキュリティレベルを保つことができます。
情報やナレッジを簡単に共有できるワークスペース「Confluence(コンフルエンス)」
ここまで業務の属人化によって懸念されるリスクやその解消・防止方法についてご紹介しました。脱属人化に向けて、チームと会社全体で効率的な情報共有を実現するにはクラウド上で利用できるコラボレーションツール「Confluence」がおすすめです。Confluenceは、以下のような「業務の属人化の解消」に有効な機能を持っている管理ツールです。
- リアルタイムで共同編集ができる
- ナレッジ紹介(新着のナレッジ、社内アクセスが多いナレッジにアクセスができる)
- 高度な検索機能がある(編集者別:ラベル別:)
- 閲覧履歴(自分が過去に見たナレッジにアクセスしやすい)
- コメント機能でコミュニケーションがスムーズに取れる
- あらゆる業務タイプに合わせたテンプレートがある。テンプレートのカスタマイズも可能
- 編集・閲覧の制限を細かく設定できる
- SlackやTeams、BOXや各種Googleサービスとの連携ができる
- バージョン(変更履歴:古いナレッジのアーカイブ)
- ファイル格納、ビューワー(pdf,Word,Excelなどの様々なファイルを格納・閲覧)
気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。
- お気軽にご相談ください。
- 各種お問い合わせ、ご質問など以下よりご相談ください。
- お問い合わせ

- 社内の情報を 蓄積&活用する
ナレッジマネジメントツール Confluence(コンフルエンス) 
- 製品について詳細はこちら
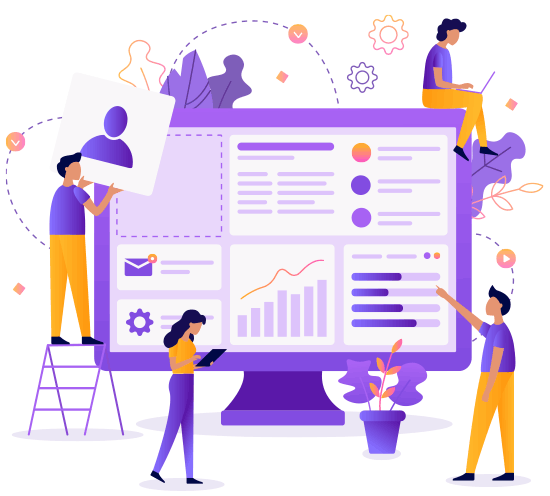
- Confluence の導入事例
- チームコラボレーションツールの有効活用で
エンジニアおよびバックオフィス部門のナレッジ共有を実現 
- 詳しくはこちら



